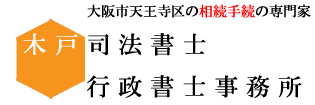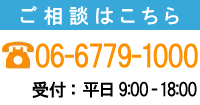改正について
概要と開始時期
令和4年度の税制改正にともない、不動産登記実務にも重要な制度改正がありました。
今年の4月1日から、中古住宅を購入する際の住宅用家屋証明書発行の要件のうち、築年数の制限が廃止されたのです。
その変更の内容とは、
登記簿上の新築日が昭和57年1月1日以降であれば、耐震基準適合証明書等の添付が無くても住宅用家屋証明書が発行されるようになった
です。
以前との比較
これまでは、対象の建物を取得した日が、新築日から規定の年数以内の場合に、住宅用家屋証明書の発行が認められるのが原則で、もし、取得日が規定の年数を超過している場合は、建築士等が発行する耐震基準適合証明書などの新耐震基準に適合していることの証明書を添付したときに限り、発行が認められていました。
これからは、新築日が昭和57年1月1日以降であれば、耐火建築物・非耐火建築物関係なく、一律で新耐震基準に適合しているとみなされるようになり、以前のような建築年数の制限無く、住宅用家屋証明書を取得できることになりました。
| 取得日 | 築年数の要件 |
| 令和4年3月31日まで | 取得日が、非耐火建築物なら新築日から20年以内、耐火建築物なら新築日から25年以内なら減税対象。 ただし、建築年数を超過していても、建築士等が作成した新耐震基準に適合している旨の証明書を添付すれば、要件を満たすものとする。 |
| 令和4年4月1日から | 新築日が、昭和57年1月1日以降なら減税対象。 ただし、新築日が昭和56年12月31日以前でも、建築士等が作成した新耐震基準に適合している旨の証明書を添付すれば、要件を満たすものとする。 |
※耐火建築物・・・石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
※非耐火建築物・・・木造・軽量鉄骨造
よって、建物の新築日が昭和57年1月1日以降の場合は、耐震基準適合証明書等の取得は不要です。
なお、新築日が昭和57年1月1日以前の建物については、耐震基準適合証明等が必要です。
メリット
この制度改正のメリットは、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の費用負担が無くなることです。
耐震基準適合証明書の発行手数料ですと、安くても2~3万円くらいはするようです。
住宅用家屋証明書は、登記の印紙代(登録免許税)の軽減のために必要なものです。
私が日頃ご依頼をいただいている案件ですと、住宅用家屋証明書が有ると、大体10~20万円くらいは登録免許税が安くなります。
また、住宅ローン減税も同様に、建物の新築日が昭和57年1月1日以降であれば、耐震基準適合証明等が無くとも住宅ローン減税の適用を受けることができます。
注意点
この築年数要件廃止の対象となるのは、建物を施行日(令和4年4月1日)以降に取得した場合に限られます。取得日が令和4年3月31日以前ですと、これまでどおり、20年または25年の縛りのままなので、ご注意ください。
根拠条文
租税特別措置法施行令 第42条第1項第2号
二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
政令第148号 第22条
新令第42条第1項、第42条の2の2第1項及び第42条の2の3第1項の規定は、施行日以後に取得をする新法第73条若しくは第74条の3第1項に規定する建築後使用されたのことのある住宅用家屋の所有権の移転の登記又は施行日以後に取得をする新法第75条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第73条若しくは第74条の3第1項又は第75条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
最後に
『【税制改正】住宅用家屋証明書の築年数の制限規定が変更になりました』いかがでしたか?
住宅用家屋証明書発行の要件変更のお知らせとそのメリットについてお話をさせていただきました。
住宅の購入には様々な出費が伴うものです。
その出費を少なからず減らせる制度を使うためのハードルが下がるのは、そのイベントに関わっている司法書士からすると、喜ばしいものだと感じます。
この記事が何かの参考になったのならば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者 司法書士・行政書士 木戸瑛治