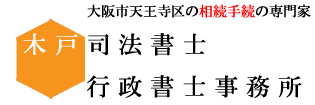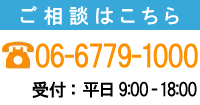はじめに
こちらは、官公署(地方自治体)の抵当権を、時効消滅を原因として抹消する嘱託登記について、実際の対応事例を用いて解説する記事です。
どちらかというとプロ(同業者)向けの内容です。
事件概要
所有不動産に関する法的な相談を受けたので、謄本を確認したところ古い抵当権が付いたままになっていることを説明したところ、その抹消登記の手続きの依頼を受けました。
ただ、抵当権自体は戦前に設定されたもので、設定当時の所有者から代を経た依頼者には、何も事情はわからないとのことでした。
そこで、抵当権者である地方自治体の担当部署に問合せたところ、当時の資料は既に残っておらず、役所の側も事情はわからない。もし、消滅時効を援用するなら、抹消手続きに協力しても差し支えないとの回答を得ました。
委任状を含めた登記書類は全て当方で作成し、抵当権者(地方自治体)から捺印をもらい、嘱託登記を代理申請しました。
合わせて、債権額は少額で、簡裁代理権の範囲内だったので、消滅時効援用も代理人として行いました。
論点整理
今回の登記には、次の論点がありました。
・官公署が義務者となる嘱託登記
・被担保債権の時効消滅による抵当権の消滅
・債権の一部弁済があった
・不動産所有者の相続による一般承継
・抵当権者の市町村合併による一般承継
添付書類
今回、登記嘱託書に記載した添付書類は、次の3つです。
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報(登記義務者からの委任状)
・一般承継証明情報(添付省略)
なお、嘱託登記の場合は、登記済証(登記識別情報)の添付は必要ありません。
登記原因証明情報の書式
今回の登記では、報告形式の登記原因証明情報を作成しました。
登場人物は、
所有権登記名義人である依頼者のA、
抵当権登記名義人のB町、
市町村合併によりそのB町から権利義務を承継したC市、
抵当権設定時の債務者兼設定者のD(Aの先祖)です。
<参考書式>
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 ○番抵当権抹消
(2)登記の原因 昭和5年4月1日時効消滅
(3)当 事 者
権利者 住所 A
義務者 B町
合併による権利義務承継者 C市
(4)不動産の表示 C市◯町1番の土地
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)昭和3年5月1日、B町とDは、下記債権を被担保債権として、本件不動産に抵当権設定契約を締結した。
債権額 金◯円 利息 年◯分 債務者 D 弁済期 定めなし
(2)昭和5年3月31日、DはB町に対して、本件抵当権の被担保債権のうち◯円◯銭を一部弁済した。
(3)昭和10年7月1日、C市は合併により本件抵当権を取得した。
(4)昭和15年3月31日が経過した。
(5)平成◯年◯月◯日、Aは相続により本件不動産の所有権を取得した。
(6)令和3年10月1日、AはC市に対して、本件抵当権の被担保債権の消滅時効を援用する意思表示をした。
(7)よって、昭和5年4月1日、被担保債権の消滅により本件抵当権は消滅した。
最後に
『時効消滅した官公署の抵当権を嘱託登記で抹消してみた』いかがでしたか?
書籍等には今回のケースに当てはまるズバリの文例が無かったので、複数の資料を参考にして、上記のような書式を作成しました。参考として、その書式を公開します。(補正はありませんでした)
実は、今回初めて嘱託登記の経験だったのですが、通常の登記申請と比べても、特に難しさは感じませんでした。
もし、一般の方が、ご自身で抵当権抹消の書類の作成や手続きをするのが難しければ、私にご相談いただければと存じます。
この記事が何かの参考になったのならば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者 司法書士・行政書士 木戸瑛治