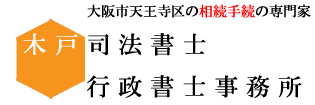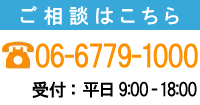はじめに
今回は、私が最近経験した後見開始の申立ての話です。
申立てが受け付けされてから家庭裁判所の審判がされるまでに、通常なら1か月程度は掛かるところ、今回書類作成を担当した申立ては、なんと申立ての受け付けから審判まで2週間程度で済みました。
流れ
後見開始の申立ては、このような流れで進みます。
- 申立ての準備
- 受理面接の予約
- 申立て書類の提出
- 受理面接
- 調査官による調査(場合によっては医師の鑑定)
- 家庭裁判所の審判
- 審判書謄本の受領
- 審判確定
はじめに述べたように、3~6までの期間は、通常1か月程度かかります。
もちろん、提出した書類に不備があったり、内容に疑問点を持たれた場合は、もっと時間が掛かります。
4の受理面接では、申立人や後見人候補者を家庭裁判所に招いて、申立てに関する事情の聴き取りや、提出書類の原本確認、後見制度の説明がされます。
ただし、新型コロナウイルスの感染が拡大して以降は、受理面接の実施は控えているようです。
実際、今回の申立てでも行われませんでした。
一方、保佐や補助類型での申立ての場合は、被支援者本人への聴取は行われます。
代理権や同意権の設定について、本人の意向を確認するためです。
なぜ審判が早くおりたのか?
今回、審判がおりるのが早くなった理由として考えられるのは・・・
- 医師の診断書に「支援を受けても判断できる能力がない」との意見があり、後見類型での申立ての必要性が明らかであった
- 後見類型で、被支援者本人への意見聴取が不要であった
- 候補者が専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)で、適格性の審査に時間を掛けずに済んだ
- 銀行の預金通帳の原本が無いため、通帳のコピーの提出ができず、取引履歴の調査ができなかった
- 銀行口座以外の財産や収支に関する資料は揃っていた
- 提出書類に不備が無く、訂正や追加提出の必要が無かった
という要素があります。
こういった色々な要素が揃ったために今回早くなっただけで、おそらく標準的な処理期間自体が早くなったわけではないと考えます。
後見開始の申立てに関する注意点
注意点としては、せっかく後見等の申立てをして裁判所の審判がおりても、
当初の目的を遂げる前に、被支援者本人が亡くなる可能性があるということです。
- 申立ての準備に1か月
- 申立ての受付から審判までに1か月
- 審判が確定して後見人が就任するまでに2週間
- 後見人が就任してから初回の財産目録提出までに1か月~1か月と3週間
成年後見人が本格的な執務を開始できるのは、家庭裁判所に初回の財産目録を提出してからとなります。(民法853条、854条)
申立ての準備が始まってから本格的な執務を開始するまでに、順調に進んでも約4か月かかることになります。
かつて、とある高齢の方が相続した不動産を売却するために、後見開始の申立て書類の作成とその後見人を務めさせてもらったことがありますが、後見が開始し、遺産分割協議がまとまって、不動産の売買契約の目処が立った段階で、被支援者の方はお亡くなりになられました。
どうしても後見制度の利用者は高齢の方が多くなりますので、数か月の間に状態が急変する可能性がある点については、あらかじめ覚悟しておくべきかと考えます。
●民法参考条文
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
最後に
『成年後見の申立てから審判までの日数が早くなった?』いかがでしたか?
依頼者の方からの質問で多いのは、費用とスケジュールに関することです。
今後、今回と似たようなケースのご依頼の場合は、一つの参考例として、スケジュールの目安の説明ができるかもしれません。貴重な経験をさせてもらいました。
当事務所では、後見開始の申立てなどの裁判所に提出する書類の作成のご依頼をお受けてしています。
ご自身で書類の作成や手続きをすることに不安なある方は、お気軽にご相談いただければと存じます。
この記事が何かの参考になったのならば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者 司法書士・行政書士 木戸瑛治